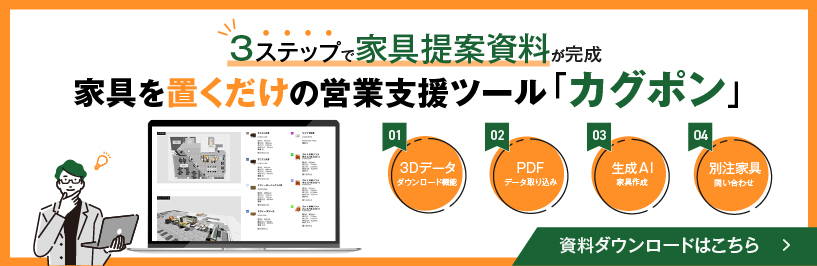建築物の設計を依頼する際、建築士と設計士のどちらに相談すべきか迷う方も多いでしょう。両者は似た名称でありながら、保有する資格や担当可能な業務範囲、法的責任において大きな違いがあります。この記事では、それぞれの特徴を詳しく解説し、プロジェクトに最適な専門家を選ぶための判断材料をお伝えします。
建築士と設計士の基本的な役割の違い
建築物の設計に携わる専門家として、建築士と設計士という職業がありますが、両者には明確な違いが存在します。資格の有無や業務範囲、法的責任の所在など、様々な観点から相違点を理解することで、適切な専門家選びができるでしょう。
建築士の定義と担当業務
国家資格を保有する建築の専門家として、建築物の設計から工事監理まで幅広い業務を担当します。建築基準法や建築士法に基づいて、建物の安全性や法令適合性を確保する責任を負い、設計図書の作成や構造計算、建築確認申請の手続き、現場での工事監理などを実施しています。
設計士とはどんな立場か
特定の資格を必要としない設計業務の担当者として、主にデザインや図面作成に従事する職業です。建築士の指導や監督のもとで業務を行うことが多く、100㎡未満の木造建築物などの小規模な建物については単独で設計することも可能で、クリエイティブな発想力を活かした設計業務が中心です。
法的な位置づけの違いを押さえる
建築士法により建築士は国家資格として明確に定義されており、一定規模以上の建築物の設計・工事監理は建築士でなければ行えません。一方で設計士という資格や法的定義は存在せず、業界内での呼称として使われているのが現状です。建築士には業務独占権があり、法的責任を負う立場にあります。
日常業務での役割分担イメージ
実際のプロジェクトでは、建築士が全体の責任者として法的手続きや構造面の検討を行い、設計士がデザインの具体化や詳細図面の作成を担当する分業体制が一般的です。建築士は最終的な判断や承認を行い、設計士は創造性を発揮してアイデアを形にしていく役割を果たしています。
建築士の種類と資格要件
建築士には3つの種類があり、それぞれ設計可能な建築物の規模や構造に違いがあります。受験資格や試験内容、取得後の業務範囲も異なるため、目指す分野や将来のキャリアプランに応じて適切な資格を選択しましょう。
一級建築士の業務範囲と取得条件
すべての建築物の設計・工事監理が可能な最上位の資格として、商業施設や高層建築物から住宅まで制限なく取り扱えます。大学の建築学科を卒業後、実務経験を積んで受験資格を得て、学科試験と設計製図試験の両方に合格する必要があります。合格率は約12%と難関資格として知られています。
二級建築士の特徴と試験要件
延べ面積300㎡以下、高さ13m以下の建築物を設計できる資格で、主に戸建て住宅や小規模な建築物を対象とします。建築系の学科を卒業していれば実務経験なしで受験可能で、一級建築士よりも取得しやすい資格として位置づけられています。学科試験と設計製図試験で構成されています。
木造建築士の限定業務と受験資格
延べ面積300㎡以下、2階建て以下の木造建築物に特化した資格です。木造建築の専門知識を有する証明となり、古民家再生や神社仏閣の修繕など特殊な分野でも活用できます。受験資格は二級建築士と同様で、建築系学科卒業者は実務経験なしで受験可能です。木造建築に特化した深い知識が求められます。
設計士の法律上の位置づけと呼称
設計士という名称は法的な根拠を持たない業界用語として使われており、建築士のような資格制度は存在しません。この違いを理解することで、依頼する際の判断基準や期待できるサービス内容を正しく把握できます。
設計士という名称の法的根拠
設計士という資格や法的定義は存在せず、建築に関する設計業務に携わる人の総称として使用されています。建築士のような国家資格ではないため、誰でも名乗ることが可能で、ハウスメーカーや建設会社、設計事務所などで設計業務に従事している担当者を指すことが一般的です。
名称独占の有無と建築士との違い
建築士は建築士法により名称独占が定められており、資格を持たない者が建築士を名乗ることは法律で禁止されています。これに対して設計士は名称独占がないため、資格の有無に関わらず使用できます。ただし、実際の設計業務では建築士の監督下で行う必要があり、単独で責任を負うことはできません。
業務範囲で比較する建築士と設計士の違い

実際の設計業務において、建築士と設計士では担当できる範囲や責任の所在が大きく異なります。法的な権限や専門知識の深さ、プロジェクトでの役割分担など、多角的な視点から両者の業務範囲を理解しましょう。
意匠設計と構造設計の担当範囲
建築士は意匠設計から構造設計まで包括的に担当でき、特に構造計算や安全性の検討は建築士でなければ行えません。設計士は主に意匠設計やデザイン業務を担当し、建築士の監督下で詳細図面の作成やCAD操作を行います。構造に関わる重要な判断は建築士が最終的な責任を負います。
施工管理や監理業務との関わり
工事監理業務は建築士の独占業務であり、設計図通りに工事が進められているかを確認し、必要に応じて施工者への指導を行います。設計士は工事監理の権限を持たず、主に設計段階でのサポート業務や図面の修正作業を担当し、現場での最終的な判断や責任は建築士が負うことになります。
設計業務の委託形態と費用相場
委託形態は基本設計から実施設計まで一括で依頼する方法と、段階的に契約する方法があり、プロジェクトの規模や予算に応じて選択できます。設計監理まで含めた総合的なサービスか部分的な業務委託かで費用は大きく変わり、建築士と設計士では料金体系に違いがあります。
現場で差がつく!建築士と設計士に必要なスキル
建築業界で活躍するためには、技術的なスキルだけでなく、コミュニケーション能力やプロジェクト管理能力も欠かせません。それぞれの職種に求められる具体的なスキルを理解し、継続的なスキルアップに取り組みましょう。
CAD・BIM操作の習熟度を高めるポイント
現代の設計業務では、CADやBIMソフトの操作技術が必須となっています。2次元図面の作成だけでなく、3次元モデリングやレンダリング技術も求められ、クライアントへの提案力向上に直結します。定期的な研修参加やソフトウェアの最新機能習得により、業務効率と設計品質の向上が図れます。
建築法規や基準への理解度を深める方法
建築基準法をはじめとする法規制の知識は、安全で適法な建築物を設計するために不可欠です。法改正の動向を常に把握し、実務での適用方法を理解することで、トラブルのない設計業務が可能です。専門書の読書や講習会への参加、実務経験を通じて知識を蓄積しましょう。
クライアント対応で求められるコミュニケーション力

施主の要望を正確に把握し、専門知識を分かりやすく説明する能力は、満足度の高いプロジェクト完成に欠かせません。ヒアリング技術やプレゼンテーション能力を磨き、建築に詳しくないクライアントとも円滑な意思疎通を図ることで、信頼関係を構築できます。
プロジェクト管理の基礎知識と実践
設計から施工まで長期にわたるプロジェクトを成功に導くため、スケジュール管理や品質管理の手法を身につける必要があります。各工程での重要ポイントを押さえ、関係者間の調整を適切に行うことで、予算内での期日通り完成が実現できます。実務経験を通じて管理スキルを向上させましょう。
建築士と設計士を選ぶ際のポイント
建築プロジェクトの成功には、適切な専門家選びが欠かせません。予算や要求内容、プロジェクトの規模に応じて、建築士または設計士のどちらに依頼するかを慎重に検討する必要があります。
予算や要望に合わせた適切な選択方法
プロジェクトの規模や複雑さに応じて、必要な資格レベルを判断しましょう。大規模建築物や法的手続きが複雑な場合は建築士への依頼が必須ですが、小規模な住宅やデザイン重視のプロジェクトでは設計士でも対応可能な場合があります。予算との兼ね合いも考慮して最適な選択を行いましょう。
過去実績の確認とポートフォリオの見方
依頼を検討する専門家の過去実績やポートフォリオを詳細に確認することで、技術力やデザインセンスを判断できます。同規模・同用途のプロジェクト経験の有無や、完成した建築物の品質、クライアントからの評価なども重要な判断材料です。実際に現地を見学できる場合は、積極的に足を運ぶことをおすすめします。
契約前に押さえておく注意点
業務範囲や責任の所在、費用体系について事前に明確化しておくことでトラブルを回避できます。特に設計士に依頼する場合は、法的責任を負う建築士が誰なのかを確認し、工事監理業務の対応方法についても取り決めておく必要があります。契約書面での確認を怠らないようにしましょう。
まとめ
建築士は国家資格を持つ専門家として幅広い建築物の設計・工事監理を担い、設計士は資格を持たない設計業務の担当者として主にデザイン面で活躍します。プロジェクトの規模や予算、求める専門性に応じて適切な選択を行うことで、理想の建築物の実現につながるでしょう。
◤カグポン◢◤
家具業界初の営業効率化ツール
家具をポンッと配置して、その場で3Dの提案書と見積もりが作れます!
▼詳細はこちら
https://www.kagupon.com/