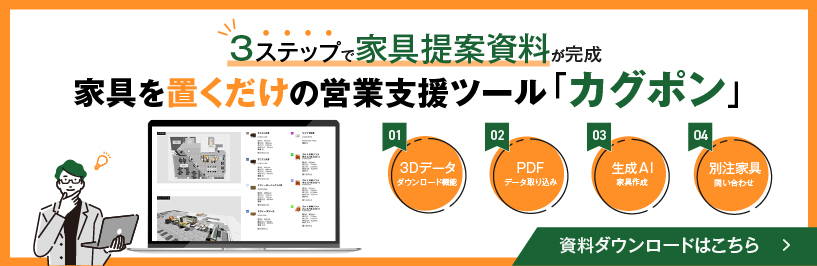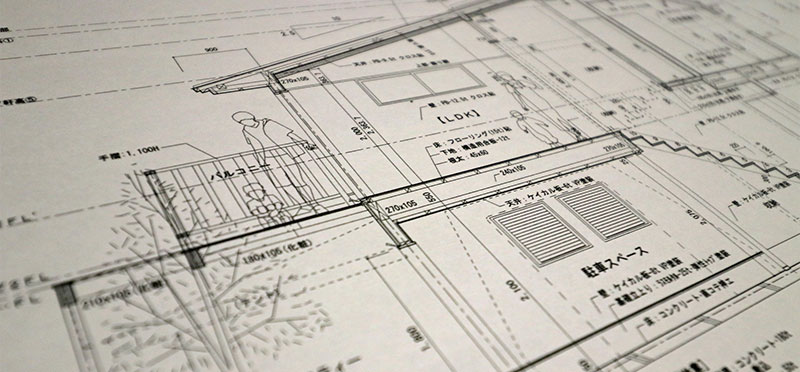テナントとして物件を借りる際、工事に関する責任範囲や費用負担が曖昧なままでは、後々大きなトラブルに発展する可能性があります。オフィスや店舗の開設・移転時には、A工事・B工事・C工事という3つの工事区分を正しく理解することが欠かせません。これらの区分を把握することで、予算計画の精度向上や工事進行の円滑化ができます。
A工事とは?オーナー責任の共用部工事を知る
オフィスや店舗の入居時に発生する工事は、責任の所在と費用負担を明確にするため、A工事・B工事・C工事の3つに区分されています。これらの工事区分を理解することで、入居時の予算計画やスケジュール管理が円滑に進み、後々のトラブルを未然に防げます。
A工事の定義と対象範囲(外壁・共用トイレ等)
建物のオーナーが全責任を負う工事形態で、主にビル全体の資産価値維持に関わる部分が対象です。具体的には建物の外装や外壁、共用トイレ、エレベーター、階段、消防設備、給排水設備の共用部分などが含まれ、ビル全体の機能維持に直結する重要な工事です。
費用負担・発注・業者選定はオーナーが実施
工事業者の選定から発注、費用負担まで、すべてオーナー側が担当する仕組みとなっています。テナント側は費用を負担する必要がありませんが、工事のタイミングや内容についてはオーナーの判断に委ねられるため、事前の情報収集が重要です。
テナントとして関与するタイミングと交渉のコツ
専有部分の設備であっても、入居時から設置されている設備は対象となる場合があります。気になる箇所を発見した際は、早めにオーナーへ相談することで、費用負担なしで工事を実施してもらえる可能性が高まります。交渉の際は具体的な問題点を明確に伝えることが効果的です。
A工事での注意点(騒音・契約書確認・スケジュール調整)
工事期間中は騒音や振動の影響を受ける可能性があるため、事前にスケジュールを確認し、必要に応じて顧客への告知を準備しましょう。契約書で工事範囲を詳細に確認し、専有部分の取り扱いについても明確にしておくことで、後々の認識違いを防げます。
B工事とは?テナント負担でも業者はオーナー指定
テナント側が費用を負担するにも関わらず、工事業者の選定権限はオーナー側にあるという特殊な工事区分です。この仕組みのため、費用面でのトラブルが最も発生しやすく、テナント側としては慎重な対応が求められます。建物全体に影響を与える可能性がある工事が対象となっています。
B工事の定義と対象(空調・照明・配管など)
テナントの専有部分でありながら、建物全体に影響を及ぼす可能性のある工事が対象です。具体的には空調設備工事、防災設備工事、分電盤工事、給排水設備工事、防水設備工事などが該当し、建築基準法や消防法などの法律に関わる工事も含まれます。
業者指定はオーナー、費用負担はテナントになる構造
工事業者の選定権限はオーナー側にあるため、テナント側は指定された業者に工事を依頼する必要があります。しかし、工事費用はテナント側が負担するため、競争原理が働かず、結果として工事費用が高額になる傾向があります。この構造を理解した上で、適切な対策を講じることが重要です。
高額見積への対応策と複数社見積もり活用
見積もり金額に納得がいかない場合は、複数社から見積もりを取得してオーナーとの交渉材料にしましょう。工事内容をC工事に変更できないか相談したり、工事範囲を見直したりすることで、費用を抑えられる可能性があります。事前の相談と交渉が費用削減の鍵となります。
原状回復対象に含まれるB工事の注意点
退去時の原状回復義務には、天井設備やスプリンクラーなどの設備が含まれる場合があります。入居時に工事区分と原状回復範囲を契約書で詳細に確認し、退去時の費用負担についても明確にしておくことで、後々のトラブルを防げます。
C工事とは?テナントが自由に発注できる内装工事
テナント側が工事業者の選定から発注、費用負担まで全てを担当する工事区分です。自由度が高く、コストコントロールもしやすい反面、業者選定やスケジュール管理などの責任も重くなります。専有部分のうち、建物全体に影響を及ぼさない範囲の工事が対象です。
C工事の範囲(照明、家具設置、LAN配線など)
テナント専有部分の内装工事、コンセントやブレーカーの増設、照明器具の設置、会社名や部屋の案内表記、壁や天井のクロス張り、床材の施工、家具の取り付け、インターネット配線工事、区画内の間仕切り工事などが該当します。建物の構造に影響を与えない範囲での工事が基本です。
発注も費用もテナント、自社業者が使える利点
テナント側が工事業者を自由に選定できるため、複数社から見積もりを取得して価格を比較検討できます。普段から取引のある業者に依頼することも可能で、工事内容や価格について直接交渉できる点が大きなメリットです。工期の調整も柔軟に対応できます。
指定業者制度がある場合の注意(高層ビル等)
高層ビルや大型ショッピングモールなどでは、管理の都合上、指定業者のみが工事を実施できる制度が設けられている場合があります。この場合、テナント側は指定された業者の中から選択する必要があるため、契約前に制度の有無を確認しておくことが重要です。
原状回復を見据えた設計・素材選定の工夫
退去時の原状回復費用を抑えるため、工事時から原状回復のしやすさを考慮した設計や素材選択を行いましょう。シンプルな内装にしたり、取り外しやすい素材を選んだりすることで、将来の原状回復費用を大幅に削減できる可能性があります。
設計士・営業目線で押さえる“工事区分チェックリスト”

工事区分を正確に把握し、スムーズなプロジェクト進行を実現するためには、契約時から完工まで一貫したチェック体制が必要です。設計士や営業担当者の視点から、実務で活用できるチェックリストを整理し、トラブルを未然に防ぐための管理手法を確立しましょう。
契約時に確認するべき工事区分表の項目
賃貸借契約書に記載された工事区分表を詳細に確認し、各工事項目がどの区分に該当するかを明確にしましょう。特に電気設備や空調設備など、ビルによって区分が異なりやすい項目は重点的にチェックし、不明点があれば契約前に必ず確認することが大切です。
図面と照らした工事項目・責任者・費用負担者の整理法
設計図面と工事区分表を照らし合わせ、各工事項目の責任者と費用負担者を一覧表にまとめましょう。工事箇所ごとに区分を色分けした図面を作成することで、関係者間での認識共有が容易になり、工事進行中の混乱を防げます。定期的な更新も欠かせません。
工事前に取り決める発注フローと調整順序
各工事区分の発注フローを事前に確立し、工事の順序と調整タイミングを明確にしておきましょう。特に異なる区分の工事が重複する場合は、事前に調整会議を設定し、工期への影響を最小限に抑える計画を立てることが重要です。
変更時の連絡網と変更契約の運用ルール
工事内容に変更が生じた場合の連絡体制と変更契約の手続きを明確にしましょう。工事区分が変わる場合の承認フローや、費用負担の変更に関する取り決めを事前に定めておくことで、変更時の混乱を防ぎ、スムーズな対応が可能になります。
成功するテナント工事の進め方と管理術

工事区分の理解だけでなく、実際の工事進行において成功を収めるためには、総合的な管理体制の構築が不可欠です。全体最適の視点から工事を管理し、各関係者との円滑なコミュニケーションを維持することで、品質の高い工事を期限内に完成させることができます。
全体スケジュールを工事区分ごとに整理する
各工事区分の工期を把握し、全体スケジュールを統合的に管理しましょう。工事の依存関係を明確にし、クリティカルパスを特定することで、遅延リスクを最小化できます。定期的な進捗確認と調整により、計画通りの工事完成を目指します。
コミュニケーション窓口設置の重要性
工事区分ごとに異なる関係者が関わるため、統一された窓口を設置し、情報の一元管理を行いましょう。定期的な会議やレポートにより、各工事の進捗状況を共有し、問題が発生した際の迅速な対応体制を整えることが成功の鍵となります。
完工後の引渡し・原状回復対応まで見据えた管理体制
工事完成後の引渡し検査や、将来の原状回復工事まで見据えた管理体制を構築しましょう。工事記録の保管や、各工事区分の責任範囲を明確にした資料の整備により、退去時のスムーズな原状回復作業が可能になり、費用削減にもつながります。
まとめ
工事区分の理解は、テナント運営における基本的なリスク管理の一環です。契約時の工事区分表確認から工事完了後の管理まで、一貫した体制を構築することでコスト削減と品質向上の両立が可能になります。特にB工事については慎重な対応が必要で、事前の準備と適切な交渉により、無駄な出費を避けることができるでしょう。
◤カグポン◢◤
家具業界初の営業効率化ツール
家具をポンッと配置して、その場で3Dの提案書と見積もりが作れます!
▼詳細はこちら
https://www.kagupon.com/